JR東日本は9日、防災科学技術研究所が整備し新幹線で導入している海底地震計情報を10日から在来線の運転規制にも活用すると発表した。この新システム導入により、緊急停止するための地震検知時間を最大約20秒短縮でき、早期の列車停止が可能になる。
海底地震計データの新規活用
新たに導入されるのは、日本海溝海底地震津波観測網(S-net)の海底地震計情報だ。防災科学技術研究所が運営するS-netは、房総半島沖から根室沖の太平洋の海底に設置された150カ所の観測点から構成される世界最大級の海底地震観測網で、2016年から運用が開始されている。
鉄道総合技術研究所とJR東日本研究開発センターでの技術的検討の結果、S-netの地震計情報を在来線全エリアを対象とした早期地震警報システムに追加導入することになった。これまでの自社地震計を用いた地震検知と比較して、地震検知から緊急停止までの時間を最大で約20秒短縮することが見込まれる。
多重化による安全性向上
JR東日本は地震時の運転規制において地震検知の多重化を進めている。気象庁の緊急地震速報、自社で陸上に設置する地震計、新幹線早期検知地震計の情報に加え、今回の海底地震計情報を活用することで、より安全な鉄道輸送の実現を目指す。
海溝型の大地震に対応でき、震源が遠方の場合では大きな揺れが沿線に到達する前に列車を緊急停止させることも可能になるとしている。一定の条件下では、非常ブレーキをより早く作動させることで早期減速が可能となり、大きな地震動の沿線到達前に列車緊急停止が期待できる。
将来的な地震対策強化
JR東日本は今年4月から、首都圏1km²あたり1基以上という高密度で地震計を配置した地震防災システム「SUPREME」の地震計情報の受信も開始した。東京ガスネットワークが整備するこのシステムを活用することで、沿線の地震動をよりきめ細かくかつ正確に把握し、従来以上に現地の揺れに近い地震動値で列車運行判断が可能になる。
首都圏の一部地域では「2020年から30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」が高いと推定されており、JR東日本はグループ経営ビジョン「勇翔2034」において究極の安全の追求を経営のトッププライオリティに位置づけている。激甚化する災害への対応力強化として、今回の海底地震計データ活用が在来線の地震対策をさらに強化することになる。



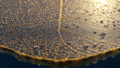
コメント