SNSでこんな文字を見かけたことはありませんか?
「およはう」(本来は「おはよう」)
「おかないすた」(本来は「おなかすいた」)
一見、意味不明でめちゃくちゃに見える文字列。でも、実は最初と最後の文字さえ合っていれば、人間の脳は意外とスラスラ読めてしまうのです。
今回は、そんな不思議な「文字の並びと脳の読み取り能力」について、科学的な視点や実際の事例を交えて徹底解説します。SNSでの話題の根源や、なぜ人は文字のズレに強いのか、その秘密に迫りましょう。
1. これを読んでみてください。
こんちには みさなん おんげき ですか? わしたは げんき です。
この ぶんょしう は いりぎす の ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか
にんんげ は もじ を にしんき する とき その さしいょ と さいご の もさじえ あいてっれば
じばんゅん は めくちちゃゃ でも ちんゃと よめる という けゅきんう に もづいとて
わざと もじの じんばゅん を いかれえて あまりす。
どでうす? ちんゃと よゃちまう でしょ?
こちらの文章読めますか?
もとのぶんしょうはこちらです。
こんにちは みなさん おげんき ですか? わたしは げんき です。
この ぶんしょう は いぎりす の ケンブリッジ だいがく の けんきゅう の けっか
にんげん は もじ を にんしき する とき その さいしょ と さいご の もじさえ あっていれば
じゅんばん は めちゃくちゃ でも ちゃんと よめる という けんきゅう に もとづいて
わざと もじの じゅんばん を いれかえて あります。
どうです? ちゃんと よめちゃう でしょ?
2. なぜ最初と最後の文字が合っていれば読めるのか?脳の仕組みを解説
この現象の科学的な背景は、認知心理学や言語学の研究で分かっています。
2-1. 脳は「全体の形」で単語を認識する
私たちの脳は単語を読む時、一文字一文字を順番に追うよりも、単語全体の形やパターンを素早く捉えています。これを「パターン認識」と言います。
このため、単語の中間の文字が入れ替わったり抜けたりしても、最初と最後の文字が合っていれば、脳は「たぶんこういう単語だろう」と推測して読み取れるのです。
2-2. 有名な英語の実験「Cambridge Universityの論文」
英語圏でよく引き合いに出されるのが、以下の英文です。
Aoccdrnig to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae.
訳すと「ケンブリッジ大学の研究によると、単語の文字の順序は関係なく、最初と最後の文字が正しい位置にあれば意味が通じる」というもの。実際、多くの人がこれをスラスラ読めてしまいます。
この現象は日本語でも同様に起こり得ることが分かっています。
3. 日本語の場合はどうなのか?「およはう」などの例
日本語は英語のように単語がスペースで区切られていないため、文字の入れ替わりが英語よりも分かりにくいと思われがちです。
しかし、ひらがなやカタカナの連続する文章でも、最初と最後の文字が合っていると、脳はそこから推測して読み取ろうとします。
3-1. ひらがな・カタカナの読み取り
例えば、「おはよう」を「およはう」とした場合、最初の「お」と最後の「う」が正しいので、脳が「あ、この言葉は『おはよう』だろう」と推測しやすいのです。
このため、SNSの軽いノリやチャットでわざと崩した文字を使っても、意味は伝わります。
3-2. 漢字の多い日本語はどうなる?
漢字は情報量が多く、文字の形自体が意味を含んでいるため、単純に最初と最後の文字が合っていれば読めるとは限りません。
ただ、漢字を含む単語や文節でも、一部の文字が崩れていても脳はかなり柔軟に読み取れます。
4. SNSやチャットで「わざと文字を崩す」理由は?
なぜ人はわざと文字を崩して書くのでしょうか?理由は複数あります。
4-1. 親しみやすさ・カジュアルさの演出
崩した文字は、堅苦しくなくフランクで親しみやすい印象を与えます。SNSやチャットでのラフなコミュニケーションにマッチします。
4-2. ユーモアやネタとして
文字崩しは笑いやユーモアを狙ったネタとして使われることも多いです。意図的に言葉をずらすことで、読者の注意を引いたり面白さを演出します。
4-3. フィルター回避・検閲対策
一部のSNSや掲示板では特定の言葉がフィルタリングされることがあります。わざと文字を崩すことで検閲を回避し、意図した言葉を伝えるケースもあります。
5. 文字が崩れても読めることを活かした面白い遊びや活用法
この「最初と最後の文字さえ合っていれば読める」特性は、さまざまな面白い使われ方があります。
5-1. 謎解き・パズル
文字の順番がバラバラでも意味を読み解く謎解きゲームやクイズが作れます。認知力や推理力のトレーニングにも最適です。
5-2. 独特の表現としてのSNS文化
特定のグループやコミュニティでだけ通じる文字の崩し方が流行し、「暗号のような言葉遊び」がSNS文化の一部になっています。
6. まとめ:文字の順番がズレても読めるのは「脳のすごい認知能力」
私たちが当たり前のように行っている「文字を読む」作業には、脳の高度なパターン認識能力が関わっています。
最初と最後の文字が合っていれば中の文字が多少入れ替わっていても、脳は「意味のある言葉」として認識してしまうのです。
SNSで見かける「およはう」「おかないすた」といった文字のズレは、この脳の特性を利用した言葉遊びやコミュニケーションの一環といえます。
この現象を知ると、文字を読むことの面白さや、脳の不思議さを改めて感じられるはず。ぜひ、次に文字が崩れた言葉を見かけたら「脳の働き」を意識して読んでみてくださいね。

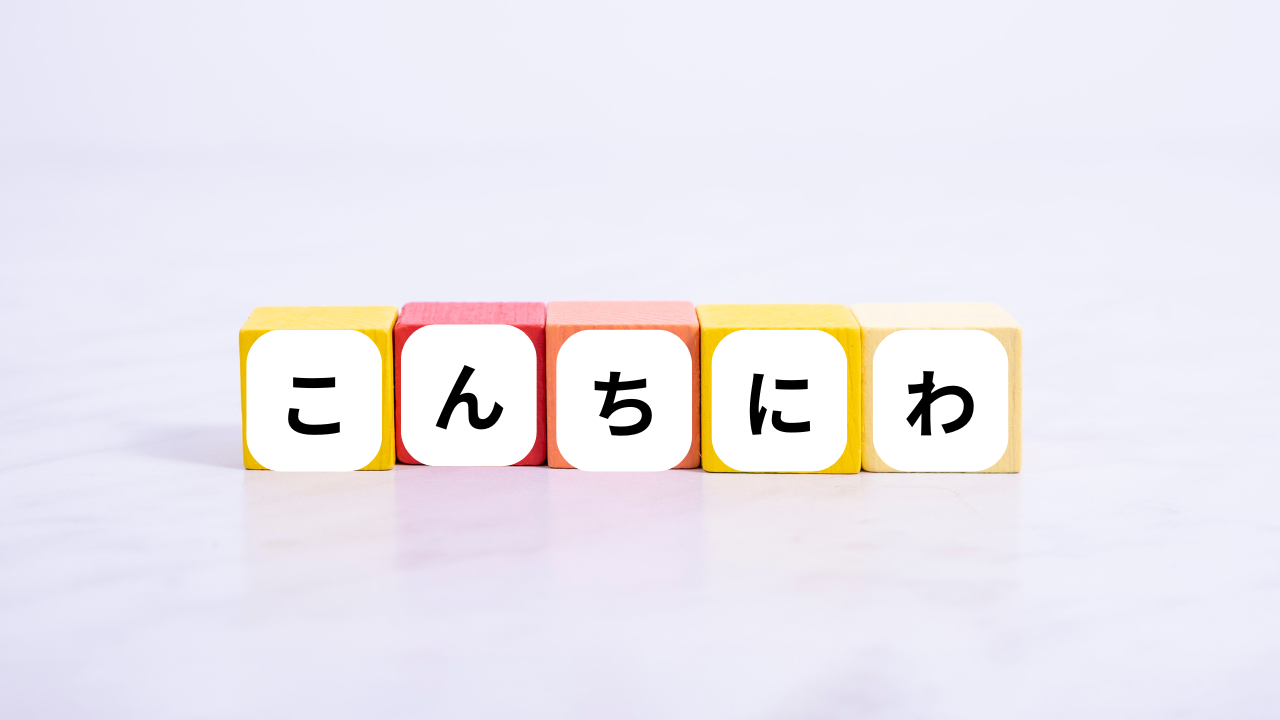
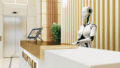
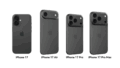
コメント