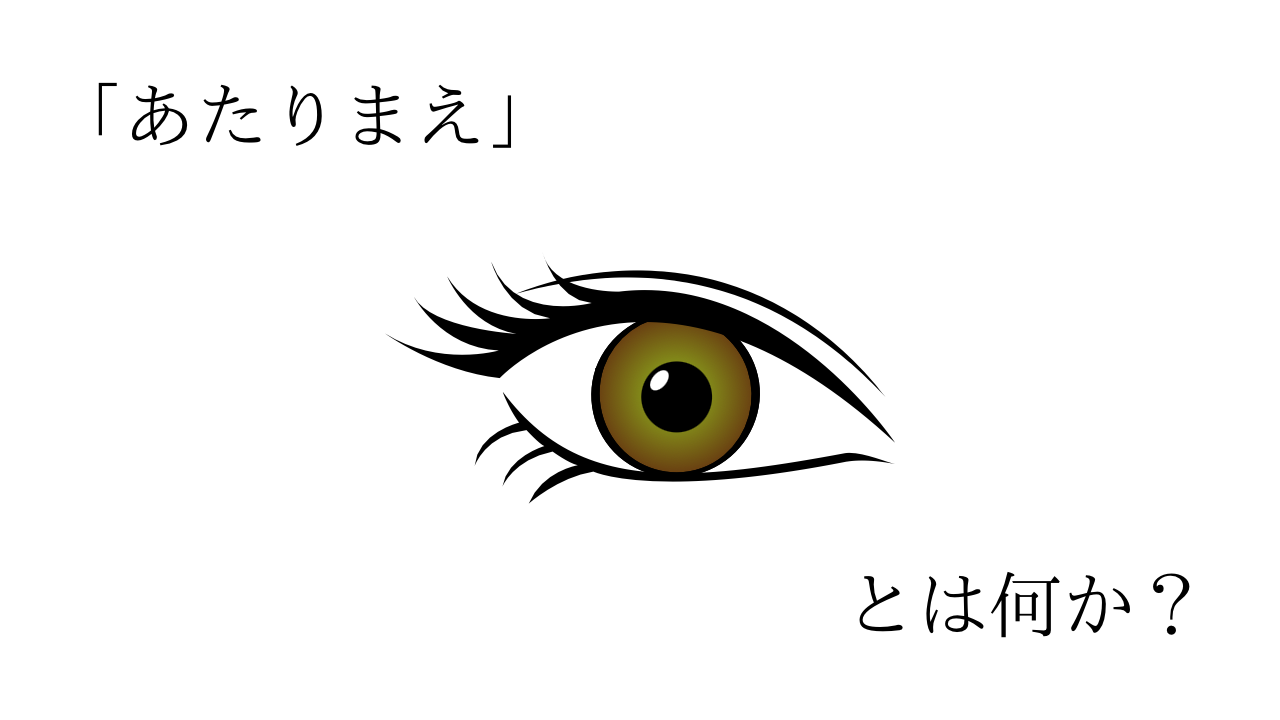私たちは日々、「あたりまえ」という言葉を何気なく使っています。「あたりまえのことをしたまでです」「そんなのあたりまえだよ」「あたりまえじゃない?」。けれども、よく考えてみると、この「あたりまえ」は誰にとっても同じ意味を持つのでしょうか? 時代や文化、立場が違えば、「あたりまえ」は簡単に揺らいでしまうものです。
この記事では、「あたりまえ」という言葉の本質を問い直し、私たちの生き方や考え方にどう影響を与えているのかを考察していきます。
「あたりまえ」の語源と意味
まず、「あたりまえ」という言葉の語源をひも解いてみましょう。語源は「当たり前」で、「当たり」は「当然」「当然の結果」、「前」は「表面」「状態」を表します。つまり「当然の状態」「普通に起こるべきこと」という意味合いです。
辞書的には、「特別でなく、ごく普通であること」「当然であること」とされます。けれども、「ごく普通」とは何を基準にしているのでしょうか?ここにすでに主観が入り込んでいることに気づかされます。
「あたりまえ」は社会がつくる幻想?
例えば、満員電車に揺られて通勤・通学すること。多くの人にとってこれは「あたりまえ」の日常かもしれません。しかし、海外の多くの都市では、そもそもそんなに人が集中して移動する社会構造ではないこともあります。つまり、これは「日本」という国、「都市」という環境が生み出したローカルルールにすぎません。
同じように、家族のかたち、働き方、挨拶の仕方、人間関係の距離感……すべてに「あたりまえ」がありますが、それは文化や時代、地域によって異なる「常識」の寄せ集めです。
「あたりまえ」に縛られる危うさ
問題は、「あたりまえ」を疑わないことによって、自由な発想や生き方が制限されてしまう点です。
・「男なんだから泣くな」
・「学校には行って当然」
・「親の言うことは聞いて当然」
こうした考え方は、長く「あたりまえ」とされてきました。しかし、時代が変わり、多様な価値観が認められるようになった今、それらが人を傷つけたり、生きづらさの原因になっていることがわかってきました。
「あたりまえ」を疑うことの価値
では、どうすればいいのでしょうか。大切なのは、「あたりまえ」と思うことに対して、一度立ち止まって考える習慣を持つことです。
「それって本当に当然のこと?」
「誰の基準であたりまえと言っているの?」
「自分はそれをどう思う?」
こうした問いかけは、自分の思考や価値観を掘り下げ、他人と違っていてもいいという認識を育てます。ひいては、他者への理解や共感にもつながっていきます。
まとめ
「あたりまえ」は、時として人を守り、時として人を縛ります。その両面を理解したうえで、私たちはより柔軟に物事を見つめることができるようになるはずです。
「これは本当に“あたりまえ”なのか?」
この問いを忘れないことが、より豊かな生き方への第一歩なのかもしれません。