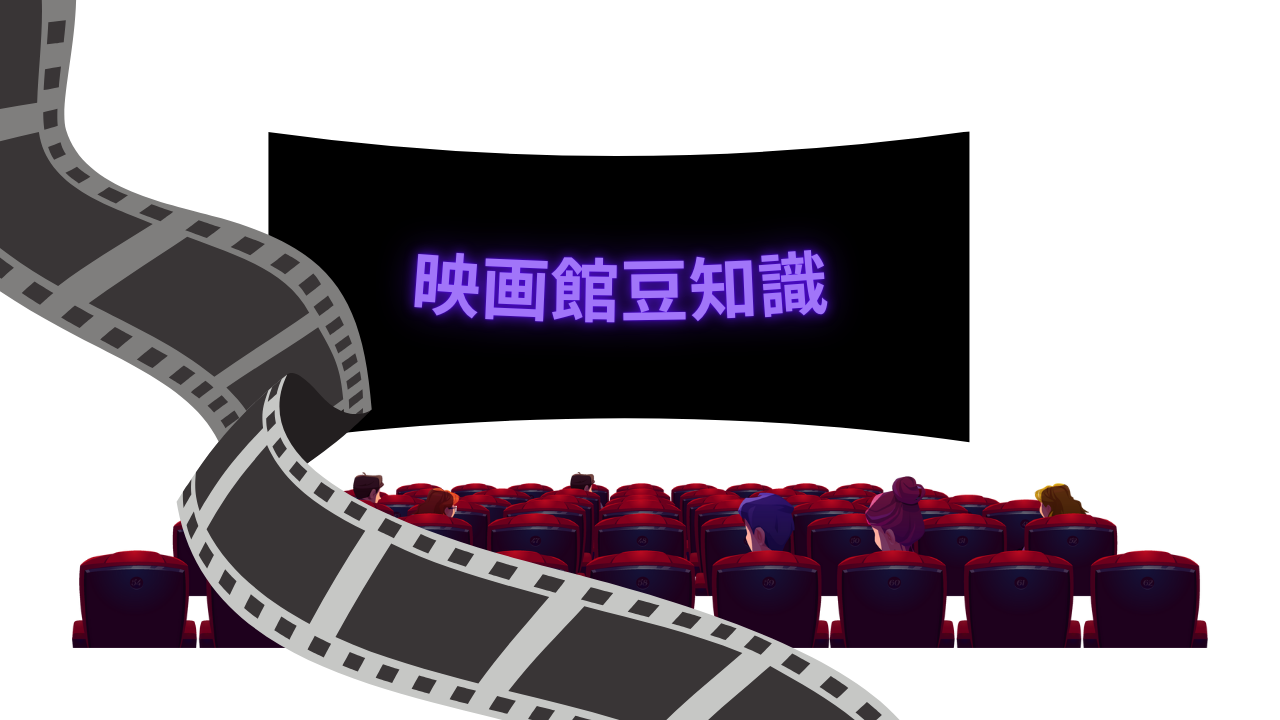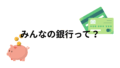出典:「TOHOシネマズ」
映画館は、ただ映画を観る場所…そう思っていませんか?
実は、そこには私たちの知らない「工夫」や「歴史」「裏話」がたくさん詰まっているのです。
今回は、映画館にまつわる面白くてちょっと役立つ豆知識を10個、たっぷり紹介します。
これを読めば、次に映画館に行くとき、きっと今までと違った目線で楽しめるはず!
1. 一番“音”が良いのはどの席?
映画館では「真ん中のちょっと後ろ」がベストポジションと言われています。
なぜなら、音響の設計上、スピーカーからの音がバランスよく届くように設定されているからです。
映画館によって多少差はありますが、だいたい最後列から3〜5列目の中央付近が理想的。映像も音も“監督の意図通り”に楽しめる位置なんです。
2. ポップコーンの香りには理由がある
映画館に入った瞬間、ふわっと広がるバターの香り。
実はこれ、わざと香りが強くなるように作られているんです!
嗅覚に訴えることで食欲を刺激し、ついポップコーンを買ってしまう人が増える…という「売上アップの仕掛け」でもあります。
ちなみに、映画館の利益の多くはフードやドリンクから生まれているんですよ。
3. チケット代のうち、映画館の取り分はどれくらい?
意外かもしれませんが、チケット代の50%以上は配給会社や映画製作側へ。
映画館側の取り分は3〜4割程度で、それだけでは運営が難しいため、フードやドリンク販売、ポイント制度などが重要になっています。
4. 映画館が暗いのは“映像のため”だけじゃない?
もちろん、暗くすることでスクリーンが見やすくなるのは大前提。
でも実は、「観客が物語に没入しやすくなる」「感情の振れ幅が大きくなる」など、心理的な効果もあるんです。
さらに照明が暗いことで、隣の人の反応が気にならず、自分の世界に入り込めるのも大きなポイント。
5. なぜ飲食がOK? 他の劇場と違う理由
演劇やクラシックのコンサートでは飲食禁止が普通ですが、映画館はOK。
その背景には、アメリカの文化的な影響があります。
映画は「カジュアルに楽しむ大衆娯楽」として発展してきたため、リラックスして観ることが前提に。
もちろん、音の出る包装やにおいの強い食べ物はマナー的にNGですが、飲食できるのは映画館ならではの特徴です。
6. 日本で初めての映画館はどこ?
日本で最初の常設映画館は、1903年に浅草で開業した「電気館」。
当時は映画というより「活動写真」と呼ばれ、弁士(ナレーションを担当する人)が解説を加えながら上映していたそうです。
この“弁士文化”は日本独自のもので、今も一部の特別上映で再現されています。
7. 映画が始まる前の「予告編」、実は逆だった?
「予告編(トレーラー)」という言葉、実はもともと映画の“後”に流していたことから来ています。
つまり、本編の“後を追う”もの=「トレーラー」だったのです。
しかし観客が本編が終わるとすぐに帰ってしまうため、今のように本編の前に流すスタイルに変更されました。
8. シネコンって何の略?
「シネマコンプレックス(Cinema Complex)」の略で、
複数のスクリーンを持つ映画館の総称です。
1990年代以降、この形式が急速に広がり、今では映画館=シネコンという時代に。
スクリーンごとに異なる作品を上映できるので、効率も観客の選択肢も大幅にアップしました。
9. 字幕と吹替、どちらが人気?
日本ではおおむね洋画アニメ・ファミリー向け作品は吹替が優勢、
ドラマ・アクション系の洋画は字幕が人気という傾向があります。
また、字幕は「俳優の演技そのものを楽しみたい人」に、
吹替は「ストーリーに集中したい人」に向いています。
ちなみに、吹替版は声優の豪華キャストが話題になることも多く、近年は宣伝にも一役買っています。
10. 映画館で一番空いている時間帯は?
一般的に、平日の午前中〜昼すぎが最も空いている時間帯です。
特に火曜・水曜あたりは狙い目。
逆に混みやすいのは、土日・祝日の夕方以降と映画の公開初日・初週末。
静かに観たい派の方は、朝の回を狙うと快適です!
おわりに|“知ってる”だけで映画館がもっと楽しくなる!
こうして見ると、映画館ってただの“映画を見る場所”ではなく、
工夫と文化、歴史が詰まった「体験型エンタメ空間」なんですよね。
ぜひこの記事で得た豆知識を活かして、次の映画館ライフをもっと楽しんでください!